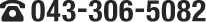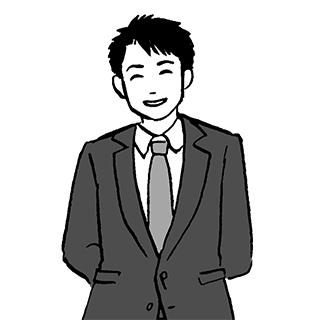【東京商工リサーチ掲載記事】名ばかり個人事業主のリスク<社会保険労務士 石川宗一郎>
今回のコラムでは「名ばかり個人事業主」や「名ばかりフリーランス」と呼ばれる問題をご紹介したいと思います。
■労働契約(雇用契約)によって生じる義務
労働者は会社と労働契約を結ぶことで、労務の提供義務を負います。一方会社は労働に対して賃金の支払い義務が生じます。付随して労働基準法や最低賃金法を遵守しなければなりません。具体的には時間外の割増賃金の支払いや年次有給休暇の付与、健康診断の実施などに関する義務です。また会社には雇用保険や社会保険への加入と保険料の支払義務も生じます。
契約する相手が業務委託者(個人事業主)であれば上記のような労働基準法の遵守や社会保険の支払義務はありません。これらの義務や保険料負担を潜脱するために業務委託契約を乱用するケースが見受けられます。実態は労働契約であるものを、業務委託契約書などを締結し、形式だけは業務委託契約してしまう手法です。
■業務委託契約と労働契約の違いとは?
業務委託契約は、請負契約と委任契約(準委任契約)の2つに分けることができます。請負契約とは、仕事の完成物を事前に決め、その完成物の納品を持って料金を支払う契約です。例えば、「新築1棟を建ててほしい」「ホームページを作ってほしい」と仕事の完成自体が目的とする契約のことです。
もう一方の委任契約(準委任契約)は業務の遂行自体を目的にする契約です。例えば、「通訳」「コンサルティング」「サーバー監視」などが準委任契約になります。
この委任契約(準委任契約)はタイムチャージで契約することが多く、その点は労働契約に似ています。しかしながら決定的に違うのは会社(使用者)の指揮命令関係の有無です。
労働契約では労働者は会社の指揮命令関係のもとに置かれます。その中で、労働時間の拘束、残業命令に従う義務、業務に専念する義務などが生じます。本来これらの義務は委任契約(準委任契約)をした業務委託契約では生じません。
■指揮命令関係にあるのかの判断ポイント
具体的には下記のような条件がそろえば指揮命令関係にある(=労働契約関係である)と判断されます。
・具体的な作業手順の指示を受けている
・作業時間の指示を受けている(時間拘束、残業指示や休憩指示、朝礼に参加しなければならない)
・作業場所が指定されている(出社しなければならない等)
・契約外の仕事の義務がある(清掃しなければならない、新人の教育をしなければならない等)
・経費や道具は会社が用意してくれる
・一社に専属となっている
裁判所、労働基準監督署、税務署などは、これらの要素をもとに個人事業主なのか労働者なのかを判断します。
■会社が労働者を業務委託にしてしまうことによって生じるリスク
先に述べましたように労働基準法や社会保険を潜脱するために労働者を業務委託契約に切り替えてしまうとどのような問題が生じるのでしょうか。過去に筆者が見聞きした事例を数例あげさせていただきます。
・労働者を個人事業主化したが、誰も税務申告をしていなかった。会社に税務調査が入り発覚し、源泉所得税の支払いを命じられた。また所得税以外にも、社会保険も未加入であったため、年金事務所からの指示で社会保険の遡及加入もすることにもなった。
・業務委託契約を解消しようとしたら、実態は労働者だったとして訴えられ、解雇無効や残業代請求を受けた。
・業務中に事故が起こり、会社は業務委託であるので労災は使えないと主張したところ、労働基準監督署に通報され、労災請求をめぐり紛争化した。
以上のように労働契約であるものを安易に業務委託契約に切り替えると、紛争化することがあります。また業務委託契約は通常の労働者に比べ会社への帰属意識も薄くなります。労働者か個人事業主かのグレーゾーンについて、最近国会でも議事に上がるようになってきました。今後、法整備も進むと思われます。
関連ブログ
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。
弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。
- タグ: