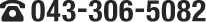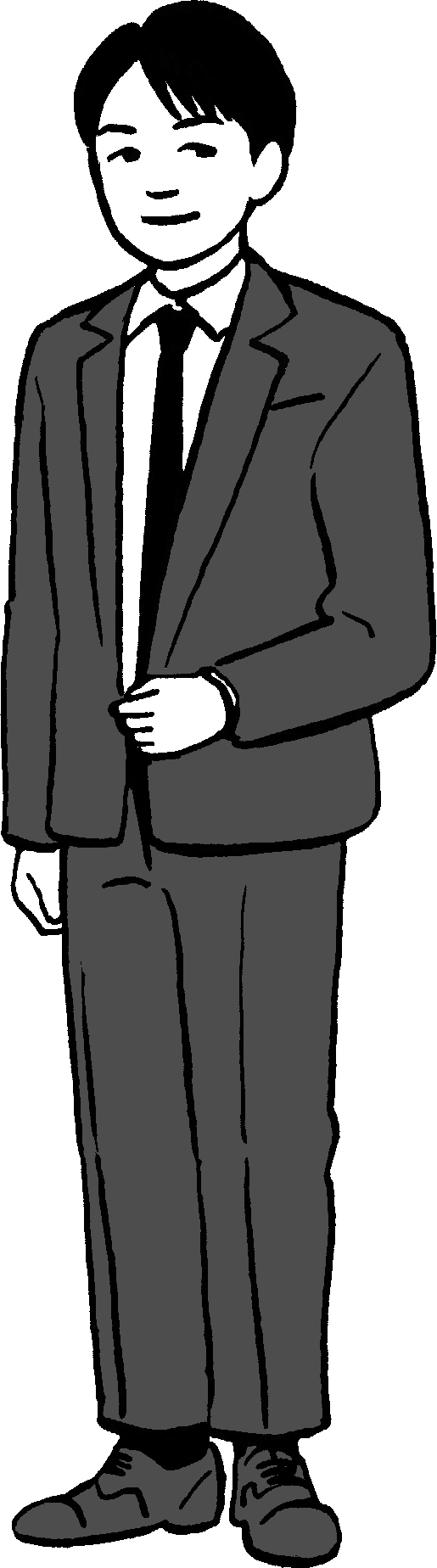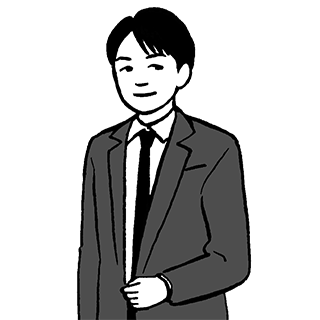【東京商工リサーチ掲載記事】福利厚生としての社内預金制度<社会保険労務士 小山健二>
人手不足や採用難といった課題に対して、その対応に苦慮されている企業様も多いのではないかと思います。そこで今回は、福利厚生制度の中の社内預金制度について触れてみたいと思います。社内預金制度は、福利厚生の一環ではありますが、労働基準法による規制もかかっていますので、その注意点等をお伝えしていきたいと思います。
1.福利厚生と社内預金制度
まず福利厚生とは、労働の直接的対価とは別に設けられた制度であり、基本的労働条件とあわせて従業員は自身の労働条件を評価します。
2020年7月に公表された「企業における福利厚生施策の実態に関する調査」(独立行政法人労働政策研究・研修機構)では、社内預金制度が「ある」と回答した企業の割合は7.9%となっています。また、「必要性が高いと思う制度・施策」に関して「特に必要性が高いと思うもの」という質問に対して、社内預金制度と回答した従業員の割合は5.2%となっています。
いずれも大きな数字ではありませんが、一定の関心があるものと考えられます。
2.社内預金制度の特徴
では具体的な社内預金制度の特徴を見てみましょう。
社内預金制度は古くからある制度で、従業員の委託を受けて会社が預金として管理を行う制度です。一般的には市場の金利よりも良い条件を付し、従業員の資産形成を支援することを目的としています。会社としても、使途を限定されない資金調達としても活用できます。以下のとおり、労使双方にメリット、デメリットはありますが、信頼関係に基づけば双方にとって有益な制度と言えるかもしれません。給与とは分けて認識されますので、金利の設定次第では、従業員側のメリットに強く訴求できます。
| 会社 | 従業員 | |
| メリット | ・従業員のロイヤリティ、意欲向上採用力向上、 ・使途制限のない資金調達 | ・比較的高利な受取利子による経済的利益 |
| デメリット | ・管理コストの上昇 ・一斉に引出しがあった際の資金繰りの対応 | ・会社の倒産等経営危機における回収可能性 |
3.社内預金制度の導入要件および運用
社内預金制度は従業員の資産を会社が預かることになりますので、導入について労働基準法による要件が付されています。内容は以下のとおりです。
| 要件項目 | 詳細 |
| 労使協定の締結と届出 | 預金者の範囲、一人当たりの預金限度額、利率/利子の計算方法、預入れ/払戻しの手続、保全方法 |
| 貯蓄金の管理に関する規程の作成と届出 | 上記協定内容の記載、労働基準監督署への届出 |
| 下限利率以上の利率設定 | 年0.5%以上(掲載日時点)の利率により月ごとに付利 |
| 受入預金額の保全措置 | 以下いずれかを講じること ①金融機関等による保証契約、②信託会社との信託契約、③質権又は抵当権の設定、④預金保全委員会の設置(貯蓄金管理勘定その他適当な措置を含む) |
| 預金の管理状況の労働基準監督署への報告 | 毎年3月31日以前1年間における管理状況を「預金管理状況報告」により労働基準監督署へ4月30日までに報告 |
| 貯蓄金の返還義務 | 従業員からの返還請求後、遅滞なく返還すること |
従業員の資産を会社が預かるということで、詳細な手続きが定められています。会社としては、預金の管理を適正に管理するための事務体制を確立することが求められます。
以上が、福利厚生としての社内預金制度に関する解説となります。従業員の定着、新規採用等はどの企業様にとっても共通の課題かと思います。お悩みの企業様があればお気軽にお声がけください。
関連ブログ
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。
弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。
- タグ: