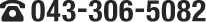【東京商工リサーチ掲載記事】ビジネス化する残業代請求②
「みなし残業」の落とし穴
「みなし残業」とは固定的な手当であらかじめ一定時間分の残業代を支給する制度のことです。その他にも「固定残業手当」「定額残業手当」など様々の呼び方がありますが、同質の制度のことです。企業がみなし残業を導入する理由としては次のメリットが想定されます。
①給与が固定額で済むので給与計算が簡略化できる。
②賃金支払の抑制になるような気がする。
③求人で賃金を大きいように見せることができる。
④残業有無に関わらずある水準の給与を保障できる。 一見便利な「みなし残業」ですが、制度設計や運用に不備があり、高額な残業代を請求されてしまうことがあります。本稿では企業が実際に注意すべき点に中心に述べて行こうと思います。
「みなし残業」の争いが起こる過程
企業Aが営業社員Bに残業代の代わりに「営業手当」を支給していたケースを考えてみます。企業Aとしては「営業手当」していたため、その他に残業手当を支給していませんでした。営業成績が振るわなかった社員Bは数年勤務した後、退職しました。退職の数週間後、Bの代理人となった弁護士より「残業代が全く支払われていないので過去2年分を支払え」と内容証明郵便が届きます。こうして残業代に請求が始まり、交渉や裁判を通して、会社Aの「営業手当は残業代の対価である」という主張と元社員Bの「営業手当は残業代ではなく、残業代が支払われていない」という主張が対立することになります。
「みなし残業代」として支給した営業手当は残業代として認められるか?
企業はみなし残業代として支給した手当(本事例では営業手当)が労働基準法第37条の時間外手当であったことに疑義が生じないような制度設計をする必要があります。
・就業規則に営業手当は時間外手当の対価であることを明記、周知している。
・雇用契約書で営業手当が時間外手当の対価として支給されることを合意している。
上記記載が抜けている。あるいは雇用契約書を交わしていないなど制度設計や運用に隙があればみなし残業制度自体が労働基準監督署や裁判所で否認されるリスクがあります。
企業によってはみなし残業代を支給しているため、実際の残業時間や残業代を把握していない場合があります。これは支給済みの「みなし残業」の手当自体が時間外手当であると認めてもらえない可能性があります。
もし私が企業Aに「みなし残業」の制度設計を相談されたらどうするか?
まずは「営業手当」の名称をから「営業時間外手当」や「定額時間外手当」といった明らかに時間外手当の固定払いであるというニュアンスに変えます。また就業規則及び雇用契約書に「営業時間外手当は時間外手当◯時間分の対価として支払う」と明記します。よく見かける例で「営業手当は時間外手当を含む」と書かれた規程を見ることがあるのですが、これはおすすめできません。営業手当の何パーセントが営業業務に対する対価で何パーセントが時間外の要素なのかという不毛な争いの元になります。
同時に検討しなければならないのが何時間分の残業代を「みなし残業代」として支給するべきか、という点です。みなし100時間と設定すれば未払い残業代は見た目なくなるように思いますが、あまりにも公序良俗に反する契約として裁判で無効化される可能性があります。現実に即した範囲が望ましいでしょう。具体的には36協定の範囲内、改正労働基準法の時間上限である45時間以内で設定することが望ましいです。
運用上時にはみなし残業代を超える時間外手当が発生した場合は超過分を精算する必要があります。
そこまでして「みなし残業」をする意味があるのか?
セミナーでここまでお話して、経営者の御婦人が「結局、普通に残業代を計算すると変わらないのではないか?」とご質問をいただいたことがあります。本稿でもメリットとして「給与計算が簡略化できる」と述べましたが、実際は超過額の検証をしなければなりません。この事務労力は通常の給与計算と何ら変わりません。また「求人で高めに見せることができる」と述べた点についても、平成29年の指針により、求人時にみなし残業代を支払う場合は、みなし残業代を除いた基本給やみなし残業の時間数等の明示が義務付けられました。昔のようにみなし残業代により求人時の賃金を水増しするようなこともできなくなりました。現行のメリットは賃金がある水準で保証できるという点だけということになります。「みなし残業」の導入は良くその意義を検討する必要があります。
関連ブログ
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。
弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。