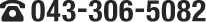【東京商工リサーチ掲載記事】タイムカードの電子化阻む壁は?
当事務所にもタイムカードの電子化に関する相談が増えています。ソフトの選定から設定までアドバイスをしています。紙ベースによる業務フローは、コロナ感染症の流行により、否が応でも非効率な部分を表に出しました。
非効率な業務フロー
以前、某企業では、社員が退職届を出してから受理されるまで「所属長・係長・部門長・人事課長・人事部長・専務・社長」と7つも印鑑が必要でした。退職希望者が就業規則に基づき1ヶ月前に退職届を提出しても、7つの判子を経て社長の手元に稟議書が届く頃には、既に退職日を超えていたのです。このように誰が見ても明らかに非効率であるのに、頑なに紙の見直しや業務フローの見直しが行われない現場に度々遭遇します。こういったイノベーションが起きにくい現場にはある種の共通点があります。
①社風が封建的であり、新しいことを提案した人が失敗すると責任を取らされる。
②現場が強く、管理部門のコントロール外である。
現場が強く、管理部門のコントロール外である。
①に関してはトップが変化するしかありません。ここで取り上げるのは②です。例えば「タイムカードを電子化しよう」と総務が提案したところ、現場の中間管理職から「今まで別に問題なかったろう?顧客対応で忙しいのであとにしてくれ!」と取り付く島もなく断られてしまいます。現場は、「高齢者が多いので電子タイムカードは無理だ」とか「現場はネット環境がない」など抵抗してきます。現実にはICカードをかざすだけのレベルだったり、ネット環境もスマートフォン1つで解決したりするので、たいしたことのない問題であったりするのですが・・・。孤立無援となった総務や人事担当者は改革を諦めてしまい、また元通りの紙のタイムカードへ戻ってしまいます。
電子化への課題
一方、電子化を実行していく企業はトップや役員が旗振り役として現場の反発を抑え込んでいるケースを目にします。会社としては如何に電子化を担当する総務や人事担当者を孤立させないようにするかが肝になります。経営者は必要性を現場に説く必要がありますし、実際に短縮した残業時間を現場に共有するなど現場に電子化の効果をアピールすることも有効です。現場がタイムカードの電子化に恩恵を感じていないとなかなか浸透しません。経験上、上手く浸透していく場合でも数ヶ月は打刻漏れや申告漏れが頻発し地道な教育や啓蒙活動が必要になります。
電子化は生産性向上のチャンス
電子化を実行できる企業とできない企業が現れ労働生産性に差が出ます。以前ならシステム導入はある程度の資本力が必要でしたが、今はクラウドを基本としたサービスが提供されており、格段に安く電子化の恩恵を受けることができます。勤怠集計に3日かかる会社と3分で終わる会社では、勤怠だけに留まらず様々な場面で業務の効率化に対する姿勢で差が出ます。働き方改革による労働時間の短縮やテレワーク実施は電子化を後押しする最大のチャンスになります。
関連ブログ
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。
弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。