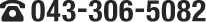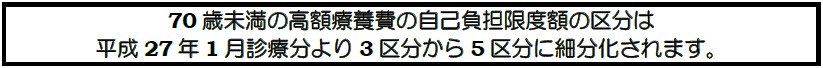平成27年1月より高額療養費制度が変わります!
法改正情報 平成26年12月16日(火曜日)
平成27年1月より高額療養費制度が変わります。
けがや病気で、病院でかかる医療費が、思った以上に高額になってしまったら…? 高額な医療費の場合、その負担は、非常に大変なものです。そこで国では、医療費の負担を減らすための制度が設けています。
高額療養費の自己負担限度額について、平成27年1月診療分より、70 歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に細分化されます。
下記に、改正内容について、まとめましたのでご覧ください。
※ 詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで
【平成26年12月診療分まで】
【平成27年1月診療分から】
高額療養費を軽減させる仕組み
なお、高額療養費制度には、上記のような自己負担額を、さらに軽減する仕組みとして「世帯合算制度」と「多数回該当制度」が設けられています。
【世帯合算制度】
世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。
(ただし、70歳未満の方については、2万1,000円以上の自己負担額のみ合算できます。)
【多数該当】
この制度は、直近の12ヶ月間に、すでに3回以上の高額療養費の支給を受けている場合に、その月の負担額がさらに引き下げられる制度です。
医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証をご利用ください
70歳未満の方が入院や外来で診療を受ける場合に、限度額適用認定証を保険証と併せて医療機関窓口に提示すると、入院時等の1ヶ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
平成27年1月1日から限度額適用認定証の区分の表記が変わります
平成27年1月1日から使用できる限度額適用認定証等の区分表記が変更になります。平成27年1月1日以降、以前の区分表記の限度額適用認定証等は使用できませんのでご注意ください。
これに伴い平成27年1月をまたぐ申請の場合は認定証が「2枚」となり、有効期間が12月31日までの分と1月1日からの分を使い分ける必要がありますので、ご注意ください。
新しい区分表記の限度額適用認定証は、12月中に郵送されます。
※「認定証」の表現について
「認定証」は、正式名称を「健康保険 限度額適用認定証」といいます。今回は、改正内容を分かりやすくするため、「認定証」と表現いたしました。また、住民税非課税については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」と申請書の名称が異なりますのでご注意ください。
Q.窓口での負担額はいくらになりますか?
〈例〉1ヵ月の総医療費:100万円、標準報酬月額:32万円、窓口負担割合:3割 の場合
【限度額適用認定証を提示した場合】
窓口で自己負担限度額 87,430円 をお支払いください。
自己負担限度額 ⇒ 80,100円 + ( 1,000,000円 - 267,000円) × 1% = 87,430円
【限度額適用認定証を提示しなかった場合】
一旦300,000円(3割)を医療機関の窓口で支払い、後日高額療養費申請により212,570円の払戻しを受けます。
ご注意ください
◇差額ベッド代、食事代、保険外の負担分は対象となりません。
◇70歳以上の方の負担に変更はありません。
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。
弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。