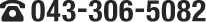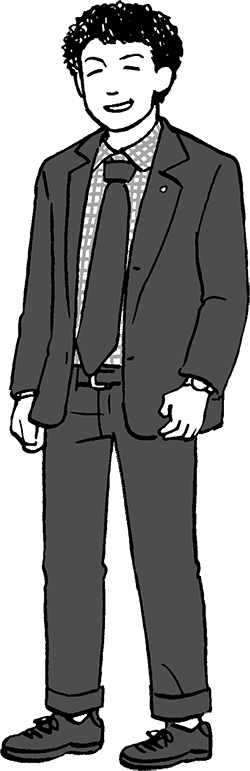【東京商工リサーチ掲載記事】4月から始まる月60時間超の時間外労働への割増率アップ~簡単そうで、意外と悩んでしまう実務について~<社会保険労務士 浅山雅人>
●月60時間超の時間外労働への割増率アップ
60時間超の時間外労働への割増率が本年4月1日より企業規模にかかわらず25%から50%となります。
長時間労働の実態がない企業では影響がないのですが、昨今の求人難で従業員ひとりひとりの労働負荷が高まってきており、その結果長時間労働が常態化している企業も多いのではないでしょうか?
また、2024年4月から上限規制の猶予がなくなる建設業、運送業のドライバー、医師についても、割増率アップのルールは本年4月より適用されることになり、本コラムが掲載される時点で未対応だった場合、未払い賃金を発生させることになります。
●60時間超の時間外労働の割増率を50%にすればいいだけだから簡単?
答えは、法定休日(※)を就業規則で特定していれば「簡単」です。仮にその定めがない場合は、意外と厄介です。
※法定休日:労働基準法で定めている「1週1日の休日」または「4週4日の休日」のこと。法定休日を上回る休日は、「法定外休日」となる。なお「法定休日」は法律上特定する義務はありません。
<設例>1日の勤務時間8時間、週休2日制(土日が休み)で、休日出勤した場合は35%の割増賃金を支払っている企業
ある月に、月~金における時間外労働が40時間、土曜出勤(3日間)で休日労働30時間を行った場合の給与計算は、40時間分の時間外労働手当(25%割増)と30時間分の休日出勤手当(35%割増)となります。
この給与計算を本年4月以降行っていたり、支払い方のルールを見直し始めると、未払い賃金を発生や他の問題を引き起こしたりする可能性があります。
ここから話しがちょっとややこしくなります。
1)就業規則で毎週土曜日を法定休日と特定している場合
上記の給与計算を4月以降行っていても問題はありません。ただ注意しなければならないのは、日曜日は「法定外休日」となりますので、月~金での時間外労働と日曜日の休日労働の合計が60時間を超えた場合は、超えた部分は50%割増された時間外手当を支払わなければなりません。日曜日の休日労働に35%割増で払っていても、その日は法定休日ではないので、時間外労働としてカウントします。
2)就業規則で法定休日を特定していない場合
<設例>の場合、1週1日の休日(=法定休日)は取れていることになりますので、70時間の時間外労働したことになりますので、結果40時間の時間外手当(25%割増)、20時間の休日手当(35%割増)、10時間の60時間超の時間外手当(50%割増)となりますので、従前の計算では未払い賃金が発生することになります。
3)就業規則で毎週土曜日、日曜日の2日間を法定休日と特定する場合
土日の休日労働を時間外労働としての扱いを受けない目的で、1週1日ではなく、1週2日の法定休日を設け、設例のような場合に60時間超の時間外手当の支払いを避ける方法です。さて、この方法が認められるかというと、結論認められません。ご参考に<行政通達>を紹介しておきます。
「労働基準法第35条に規定する週一回又は四週間四日の休日(以下「法定休日」という。)以外の休日(以下「所定休日」という。)における労働は、(中略)、時間外労働に該当するため、法第37条第1項ただし書の「一箇月について60時間」の算定の対象に含めなければならないものであること」(基発第0529001号:平成21年5月29日)
4)法定休日は35%割増、時間外労働および法定外休日は共に時間外労働扱いで計算
コストアップを回避するために、60時間超時間労働の割増率アップ改正の4月1日をもって就業規則を見直し、法定休日のみ35%割増にする方法があります。
これは、労働基準法第1条第2「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」に抵触し、労働条件の不利益変更に当たるため、お勧めできません。各労働者から個別同意を取り付ける必要があるうえ、その過程で労務トラブルに発展していく可能性がありますので要注意です。
ーーー
いかがでしょうか?実務面で意外と厄介な問題が起きうることがご理解いただけましたでしょうか?
実務上お困りごとがございましたら、エフピオまでお気軽にご相談ください。
関連ブログ
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。
弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。