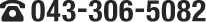【社労士のコラム】定年退職後の健康保険はどうなる?~同日得喪と定年退職後の健康保険の行方~<社会保険労務士 石川宗一郎>
前回のコラムにて、定年を迎えた人の対応の流れについてご説明いたしました。
今回は、定年退職後の健康保険について解説いたします。
前回コラム
https://fpeo.co.jp/blog/blog-5376-copy/
すぐに社会保険料が下がる!同日得喪の仕組み
定年退職後、再雇用時の給与は一般的に下がる傾向にあります。
参考コラム
通常、基本給や固定的賃金が上がったり下がったりした場合、変更月から3カ月間の総支給額の平均額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上差が出た場合、随時改定(月額変更届)を行います。
そうすると、再雇用後の賃金が下がった場合、3カ月間は従前の高い保険料のままとなり手取り額が少なくなってしまいます。
これを避けるために設けられた制度が「同日得喪(どうじつとくそう)」です。
60 歳以上の方が定年退職や契約更新で給与が下がる場合、「資格喪失届」と「資格取得届」を同時に提出することで、3カ月待たずとも下がった月から標準報酬月額を改定することができます。
随時改定の場合は、標準報酬月額の等級差が2等級以上あることが要件ですが、同日得喪の場合は等級差が1等級でも適用となります。
同日得喪は定年再雇用時だけでなく、例えば61歳の契約更新時に給与が下がった場合も対象となります。
必要書類は再雇用後の雇用契約書と就業規則の定年の箇所、保険証(家族分を含む)が必要となります。
その他必要書類は加入している健康保険組合等で異なりますので、ご確認ください。
喪失をし、取得をするため、保険証の番号が変わりますので通院されている方はご注意ください。
定年退職後の健康保険
定年退職後、再雇用をせず本当に退職となる場合、ご自身で何かしらの健康保険に加入することになります。
加入する健康保険は下記の3つです。
(1)国民健康保険に加入
(2)前職の健康保険の任意継続被保険者として加入
(3)ご家族の健康保険の扶養に入る
毎月収める保険料などを比較のうえ、選択された健康保険にお手続きください。
(1)の場合、お住まいの市町村の国民健康保険の係へご相談ください。
保険料は世帯の収入等、市町村によって計算方法が異なりますので直接市町村にお尋ねください。
(2)の場合、前職の健康保険組合(もしくは協会けんぽ)へお手続きください。
任意継続の要件は下記の通りです。
・退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があること
・退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
申請期限の20日以内は必ず守らなければなりません。1日でも過ぎると手続きができませんのでご注意ください。
保険料は、退職時の標準報酬月額に健康保険料率(40歳以上65歳未満の方は、介護保険料率が含まれます。)を乗じた額が保険料となります。
ただし、保険料には上限があります。上限は健康保険組合(もしくは協会けんぽ)により異なります。
(3)の場合、保険料はかかりません。
ただし、被扶養者になるための条件は、日本国内に住所(住民票)を有しており、被保険者(家族)により主として生計を維持されていること、および次の①②いずれにも該当した場合です。
①収入要件
年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
②同一世帯の要件
ア.被保険者と同居している必要がない者
配偶者
子、孫および兄弟姉妹
父母、祖父母などの直系尊属
イ.被保険者と同居していることが必要な者
上記ア以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
必要書類は健康保険組合(もしくは協会けんぽ)により異なります。
関連ブログ
定年は65歳に引き上げになるんですか? <コンサルタント松岡藍>
みなさん、こんにちは。 社会保険労務士法人エフピオの松岡藍です。 さて、今回は「定年って65歳にしなきゃいけないんですよね?」とお客様から受けたご質問をテーマにお話していきます。 …
定年を迎えた人の対応の流れ~再雇用後 嘱託社員の労働条件の決め方~
令和3年4月1日より、高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの「就業確保」が努力義務化されました。とはいえ、努力義務のため実際に70歳までの継続雇用とする企業は少ない印象です。 今回は、定年を迎…
「同一労働同一賃金」時代における、60歳定年後の賃金の決め方 ~ちょっと気になる数字のご紹介~
1.令和3年4月1日より中小企業にも「同一労働・同一賃金」 大企業にはすでに適用されている「同一労働・同一賃金」が、中小企業においても業種のいかんにかかわらず、適用されます。また、高齢法も本…
定年を迎えた人の対応の流れ~再雇用後 嘱託社員の労働条件の決め方~<社会保険労務士 石川宗一郎>
前回の労務コラムにて、令和3年4月1日改正の高年齢者雇用安定法について、ご説明いたしました。今回は、定年を迎えた方の対応の流れについて、詳しく見ていきましょう。 https://fpeo.c…
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。
弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。