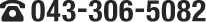【社労士のコラム】70歳継続雇用を見据えた高年齢者雇用<社会保険労務士 石川宗一郎>
令和3年4月1日より高年齢者雇用安定法の改正 70歳定年にしなければならない?
少子高齢化が急速に進み、労働力人口が減少する中、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、高年齢者雇用安定法が改正となります。
今回の法改正では、70歳までの「就業確保」が努力義務化されます。
「努力義務」のため、義務ほど強制力はなく必須ではありませんが、労働力人口が減少し、人材不足の中、中小企業にとって働くシニアの活用はしたいところです。
70歳までの「就業確保」となっているため、定年を70歳にしなければならない、わけではありません。
今回の法改正「高年齢者雇用安定法改正」で対象となる事業主・措置は下記の通りです。
<対象となる事業主>
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主
<対象となる措置>
次の①~⑦のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努める必要があります。
①定年の廃止
②現在の定年の延長
③65歳以上の継続雇用制度の導入
④他企業への再就職制度の導入
⑤フリーランスによる就業制度の導入
⑥起業による就業制度の導入
⑦社会貢献活動への従事制度の導入
①~③の措置は、過去の法改正でもあった「雇用確保」の考え方です。
④~⑦の措置は、自社の雇用ではなく、高年齢者の「就業確保」です。
他企業や兼業・副業、起業を支援し、何かしらの方法で高年齢者が社会で活躍できるような措置を取ってね、という考え方になります。
定年延長のメリット・デメリット
努力義務となっていますが、弊所のお客様でも定年を60歳から65歳、70歳に延長するケースが増えています。
医療・介護業や建設業等、定年を過ぎても現役で活躍している職種・業種は定年を延ばした方が既存の従業員のモチベーションにもなりますし、求人の際に有利になるメリットがあります。
デメリットとしては、60歳以降の退職金・昇給・賞与をどう設計するのか、定年後継続雇用をしている人(62歳等)の雇用区分をどうするのか。
退職金の勤続年数の算出を従来通り60歳までにするのか、定年年齢までにするのか。昇給を60歳までで打ち止めするのか、役職定年を定めるのか・・・
それぞれの会社によって対応策は異なりますので、ご相談いただければ幸いです。
次回は、定年を迎える人の対応についてご紹介いたします。
執筆 社会保険労務士 小林 沙奈江
関連ブログ
知らなかったではすまされない! 「労働関連法改正のポイント と実務対応セミナー」のご案内 令和3年2月3日(水)開催
同一労働同一賃金に関する最高裁判決、高年齢者や障害者の雇用の改正と、自社の対応を見直しておかなければならない重要な判決・法改正などが続いています。 今回のご紹介させて頂く「労働関連法改正のポイント …
70歳定年法/2021年4月から実施の見通し 定年60歳のわが社は大丈夫?
■そもそも定年年齢実態はどうなっているのか? <厚生労働省就労条件総合調査の概況/平成29年>によると、定年制を定めている企業の割合は95.5%、このうち定年年齢を一律に定めている(職種別に定…
経営に与える影響が大きい年金制度の改正
短時間労働者の社会保険適用拡大、年金の受給開始年齢を75歳まで引き上げる等の年金改革法が令和2年5月29日に成立しました。働く高齢者の年金を減りにくくするなどして高齢者の就労を後押しするほか、パート…
あれ?ねんきん定期便のレイアウトが変更されている!ねんきん定期便の変更からみる、高齢者雇用と年金制度改革
1.平成31年度送付分の「ねんきん定期便」のレイアウトが一部変更に 日本年金機構のホームページによると、平成31年度送付分(平成31年4月以降)のレイアウトが一部変更になっています。下記は、…
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。
弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。