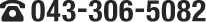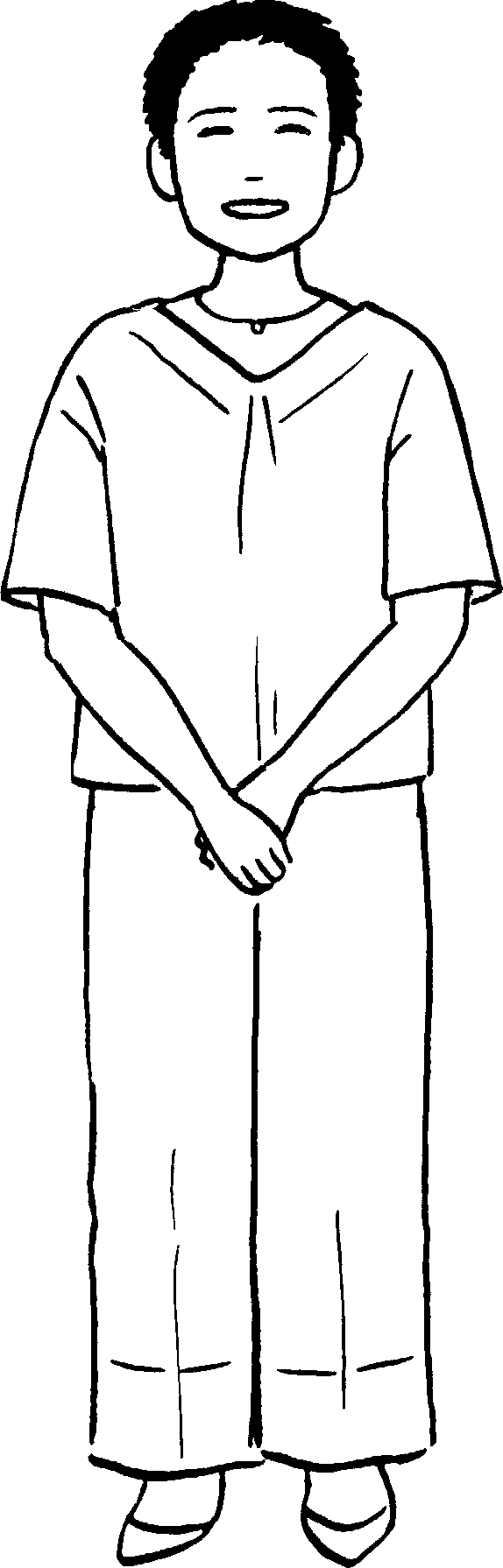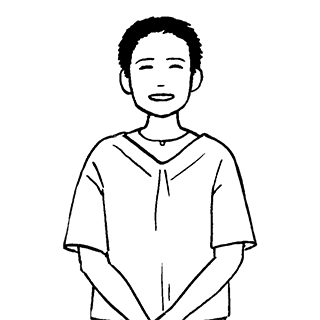【社労士のコラム】不妊治療のための休暇制度って必要ですか?
筆者は、本「労務のコラム」の執筆の際、お客様からの実際のお問い合わせをもとに、加筆修正を行いながら、現実に発生した内容により近い、旬な、リアルな情報をお届けするように心がけています。本日のテーマも、そのようなお問い合わせを基にしたケースです。
昨年来、女性従業員の多い企業様から、表題のようなお問い合わせをいただいております。時代を感じるお問い合わせですね。まずここで統計データをご紹介しましょう。国立社会保障・人口問題研究所の「2015年社会保障・人口問題基本調査」によると、実際に不妊の検査や治療を受けたことがある(または現在受けている)夫婦の割合は、全体で18.2%、5.5組に1組の割合です。子どものいない夫婦に限った場合は、28.2%だそうです。2015年に51,001人が生殖補助医療(体外受精、顕微授精、凍結胚(卵)を用いた治療)により誕生しており、全出生児(1,008,000人)の5.1%にあたるそうです。(日本産科婦人科学会「ARTデータブック(2015年)」、厚生労働省「平成27年(2015)人口動態統計の年間推計」)
さて、そうなると、働きながら不妊治療を受ける従業員の方は、年々増加傾向にあることは、想像に難くありません。厚生労働省の調査によれば、実に16%が、仕事と不妊治療との両立ができず、離職しています。国もパンフレットを作成したり、啓蒙活動を通じて、不妊治療への理解や仕事との両立に理解を呼びかけてきたところですが、2021年4月に、新たに助成金というかたちでの支援も始まりました。
助成金の内容は、本コラムの後半にお知らせするとして、休暇制度については、一部の大企業を中心に取り組みが行われてきているところです。なかなか中小企業においては、体力的な問題、負担の問題、代替要員の問題、復帰に向けてのプロセスづくり、なにより職場の理解、といった問題で、進みずらい現状にあります。ただ、そんな中でも、採用力、定着力、福利厚生の面で、お問い合わせいただいているとおり、休暇制度の新設を検討いただいている企業様もいらっしゃいます。休暇制度以外にも、無給の休職制度、年次有給休暇の失効分を積み立てて不妊治療のために再利用できる制度、治療費の貸付制度、なども取り組み事例がいくつかご紹介できますので、制度設計をご検討される場合は、一度お声がけください。
さて、不妊治療に関する助成金の内容です。両立支援等助成金に、新たに不妊治療両立支援コースが加わりました。順に対象、支給要件、支給額をお知らせします。
支援対象となる事業主:不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度について、次の①~⑥のいずれか又は複数の制度について、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度を利用させた中小企業事業主
① 不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、② 所定外労働制限制度、
③ 時差出勤制度、④ 短時間勤務制度、⑤ フレックスタイム制、⑥テレワーク
支給要件:(1)-(4)のすべてを満たすことが必要 (1)不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズ調査の実施
(2)整備した上記①~⑥の制度について、労働協約又は就業規則への規定及び周知
(3)不妊治療を行う労働者の相談に対応し、支援する「両立支援担当者」の選任
(4)「両立支援担当者」が不妊治療を行う労働者のために「不妊治療両立支援プラン」を策定
支給額:要件を満たせば、A,Bそれぞれが支給
A「環境整備、休暇の取得等」
支給要件の全てを満たし、最初の労働者が、不妊治療のための休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用した場合
1中小企業事業主 28.5万円<36万円>
B「長期休暇の加算」
上記Aを受給した事業主であって、労働者に不妊治療休暇制度を20日以上連続して取得させ、原職等に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合
1中小企業事業主 28.5万円<36万円> 1事業主当たり1年度に5人まで
さらに、表題の不妊治療のための休暇を新たに導入したい場合には、先日弊所のホームページでも取り上げました、こちらの助成金の活用も可能です。「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)https://fpeo.co.jp/news/news-5649/
- 支給対象となる事業主:不妊治療等のために利用できる特別休暇制度(多目的・特定目的とも可)を導入した中小企業事業主
- 対象経費:外部専門家によるコンサルティングや就業規則等の作成・変更などの休暇制度の導入に関する経費
- 支給額:上限50万円(所得経費の3/4。一定の要件を満たした場合4/5)
執筆 津田 千尋
関連ブログ
働き方改革に取り組む会社への助成金が新設されました
政策に左右される助成金 厚生労働省関連の雇用に関する助成金のほとんどが、国の政策によって創設されます。近年の代表的な助成金と言えば、非正規雇用労働者の正社員転換、待遇改善を図るために、非正規…
タイムカードの電子化阻む壁は?
当事務所にもタイムカードの電子化に関する相談が増えています。ソフトの選定から設定までアドバイスをしています。紙ベースによる業務フローは、コロナ感染症の流行により、否が応でも非効率な部分を表に出しまし…
柔軟な働き方の推進と、労働時間の適正管理の両立について<社会保険労務士 小山健二>
ライフスタイルの多様化やITの発展により、柔軟な働き方へのニーズが高まり、労働者に一定の裁量を与えてあげたい反面、企業側が労働時間や人件費を適切に管理しなければならず、そのバランスが難しいというお悩…
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。
弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。